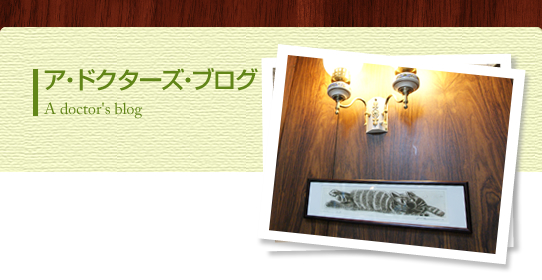2026年2月24日 (火) 09:22
児山隆監督 カルチャー・パブリッシャーズ 吉祥寺アップリンク
2026年公開映画/2026年に観た映画 目標52/120 6/24
いろいろと評判が良いので、何も知らずに予告編も観ないで来ました。
茨木県東海村の田舎の高校生である朴秀美(南沙良)はラッパーを弓見ながらも家にも学校にも居場所が見いだせず・・・というのが冒頭です。
いろいろと欠点もある映画かも知れません。違和感が無いわけではないけれど、それなりに心躍る瞬間もちゃんとある映画でした。作り手の心意気は十二分に感じました。
恐らく、原作を読んでみないといけない感じの創り込み。そしてそれぞれの文化、カルチャーに対して少なくとも敬意を感じさせる小道具であり、話しの細部にもきめ細やかな配慮を感じさせてくれます。
話しとしてもなかなか面白いですし、まぁ普通に高校生を主人公にした「テルマ&ルイーズ」と言えなくもない。しかも今の日本だとこれ男性に置き換える事が出来ないのは2000年代からこっちずっと続いてて、まぁしょうがない。
主演の2名、南沙良さんと出口夏希さんはなかなか頑張ってる。本当は頑張ってるって観客が思わないくらいの感覚の方が個人的な好みではあるけれど、その、頑張ってるが評価にも繋がってる部分もあり、うん。
お仕事映画、犯罪映画としてはもう少しリアルに寄せると難しい展開なのかも知れませんがリアリティラインとしては許せるし飲み込めるので、良かったと思います。
正直、劇伴、いらない部分多々あったように感じます、もっと効果的に使った方が良かっとも思います。でも、その分分かりやすくはなったのかも。
そう、私のようなおじいさんに向けて作られているわけじゃない。
多分若者の人たちが観て楽しめる作品にする為に、これで正解。
若者という自覚のある人にオススメします。
2026年2月20日 (金) 09:33
ディヴィッド・フランケル監督 20世紀フォックス Amazonprime
2026年公開映画/2026年に観た映画 目標52/120 5/23
いろいろあって観る事にしました。
ジャーナリスト志望のアンドレア・サックス(アン・ハサウェイ)はアポイントが取れた雑誌「ランウェイ」に向かうのですが・・・というのが冒頭です。
大変に面白おかしく、非常にアッパーな映画です、確かに楽しいですし、まぁ美形の方々が演じていますので、とにかく美しい。
ファッションについての知識が無い私が観ても、うきうきします。
アン・ハサウェイがとにかく美しく可愛く綺麗!
女性の人たちにオススメします!
全人類の半分の皆さまにエールを送ります~着飾って綺麗になってサイコー!
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
としたい所なんですよ私だって・・・
でもいいですか、全然、全然乗れないです・・・相当にバカにならないとこの映画を楽しむの難しいです・・・
ジャーナリスト志望の主人公アンドレアであるアン・ハサウェイは、ファッションに興味が無い、普通の人で、だかからこそ、彼女が何故ファッションに興味が出たのか?上司であるミランダ・プリーストリーであるメリル・ストリープの仕事、もしくはセンス、あるいは審美眼について、理解する場面ポイントが必要で、恐らく、それはナイジェル・キプリングことスタンリー・トゥッチの解説が肝なんですけれど・・・
この説明というか、説得というか、全然上手くないんです。ファッションが重要であるという人に対しても敬意を払え、大切に思っている人の事を考えろ、という意味でしかない・・・
それだと、どんな立場や好みの人が居ても良いし、尊重するのは私も当然だと思うし、大人の社会人であれば、普通はやると思います。まして仕事にしているわけで、興味が無くとも仕事なんですから、知識を増やしたり、仕事として真摯に学ばなければならないですけど、ナイジェルの説明では、そうはならないんですよね・・・つまり、ナイジェルの説明だと、ファッションに興味のないアンドレアのような人にも敬意を払う事になるんですよ。それぞれみんん違って良いです。が、ミランダの仕事の一端を理解する、という戸張口にさえ立ててないんですよね・・・
だって、ファッションである必要はなくないですか?どんな仕事であっても、好きな人に対して否定的な態度で接するな、という事は理解出来るけれど、ファッションの重要性が無いんです・・・
だからファッションの意味、着飾る、流行の意味が、全然説明されない。
ので、どう感じるか?というと、金をかけ、個人のセンスのみの、メリル・ストリープの判断だけが絶対に正しく、異論をはさむ事が出来ない状況で、会社の服を勝手に上司であるナイジェルの判断でいろいろ貰って着飾ってなんだかみんなに認めてもらいつつ、最後はその立場を捨てて、なんならその為に貰った服飾の全てを、同僚に譲ってしまう、ファッションに対しても結局何も分からないまま、コネだけで他の職場に移っていった頭が悪い美形の女子の話し、に見えるんですよ・・・
で、大ヒットして2やるそうです・・・
そりゃ私が女で着飾る事の意味をある程度体感していたとして、ですよ、でもいくら何でも自分がアン・ハサウェイと同じくらい美形という自覚は無いでしょうし、会社の服を上司に大量に譲ってもらうというのもどうかと思うし、メリル・ストリープのワガママに対して、自分に気のある男のコネを使って出版前の、絶対に流出させてはならないであろう書籍を勝手にコピーして子供に渡すって、マジで狂人の沙汰ですよ・・・仮にも出版業界に、しかもジャーナリスト志望なのに、ここに全然拘りがないなら出版業界に居ちゃダメな人ですよ・・・
あなたが業界のトップシークレットとして大切に扱ってる出版前のデザインを、勝手にコピーして他者に渡したら、その雑誌からは絶対に解雇でしょうし、それを分かってワガママとして命令するメリル・ストリープも狂ってます。
まぁこのメリル・ストリープが本当に嫌味な嫌な奴なんですけれど、メリル・ストリープ以外の人にはやれなかったでしょうね・・・恐らくもっと批判されたと思います・・・
少し、ああ、と思ったのは、アン・ハサウェイが、メリル・ストリープの仕事について、もしあの人が男の人だったらあなたも有能って認める、みたいな発言をしていて、これ、本当にそう思ってる、もしくは全女性がそういう考えなんだとしたら、これは本当に恐ろしい考えで、自らの意見は無いが、上司の判断だけは無批判に受け止めるし、判断が早い人は素晴らしい、と思っている事になるので、恐ろしい。
でも恐らく、結構な割合で、そうなんのかも・・・そしてそう思わせてしまっている男性が多いのは認めるけど、ヤバいなぁとは思います・・・
あとなんでもコネで解決、金も会社から出てるわけで、う~ん・・・
マジでファッション業界、虚飾!と思ってしまいました・・・というような事を書かなければ良いのですが、備忘録として・・・
あと、あ、と思った点はJ・マキナニーの名前が出てきた、という事です。まだ頑張ってるのかな・・・「ブライト・ライツ・ビッグ・シティ」と「ランサム」は良かったけど、その後の「モデル・ビヘイヴィア」はまるでダメでしたし、その後翻訳すらされなくなってしまいましたけど・・・
2026年2月17日 (火) 08:57
ローラ・ワンデル監督
2026年公開映画/2026年に観た映画 目標52/120 5/22
2025年公開の評判良い作品だったので。
これは見逃していたのを後悔するレベルで素晴らしい作品でした・・・
小学校に上がったノラは兄であるアベルと一緒が良いのですが・・・というのが冒頭です。
大人には理屈が通用しますし、社会性のあるルールの中でのコミュニケーションなので、それが普通と思いますけれど、子供にとっては全然違うルールで動いていますし、そのルールが子供だけだと全く違ったモノに変容します。
そして非常に残酷になれる。
まず主演の子、というか俳優が凄い。
恐らく妹が主演で7歳くらいか?未就学児に見える。しかし、もう既に物憂げな表情を浮かべられるの、恐ろしい子、です。マヤ、です、マジで。
そしてお兄ちゃんアベルですが、背丈は低めなんだけれど、既に哀愁を醸し出せる男・・・怖い!どういう演技指導をしているのか?気になります・・・しかも恐らく歯牙の交換時期から、10歳、もしくは11歳と思われ・・・そんな年齢で、どうしてそんな表情が出来るの?おじいさん、心配になってしまいます・・・
2人とも、飛び抜けた美形では無いのかも知れませんが、私の感覚だと、整ってるし、ふとした瞬間の、瞳の美しさ、瞳の黒目の部分の大きさに反して、瞳孔が小さい事で生まれる気品のようなモノが、2人ともにある。
またノラの斜め後ろからのカットで観られる、幼少期にしか見られない骨格と筋肉の動きの拙さゆえの、もごもごとした動きが皮膚の下の骨の動きが起こしていると思いにくい皮膚の動きも相当にヤバいです。
この年齢だと、私の感覚では男女差なんて無いと思っていましたが、確実にあるのも、怖い感覚になります。
ネタバレ無しではあまり言える事が無いけれど、子供の世界では大人は部外者なんです。
それとこの映画はフランス語を喋っていますが、ベルギーの映画のようです。ルクセンブルグからも近い、実家から行けるはず。
あなたがもし子供時代を過ごしていた自覚があるなら、それだけで観る価値があります。
子供時代の事を覚えている人、覚えていない人にオススメします。良作です。
アテンション・プリーズ!
ここからはネタバレありの感想になります。未見の方はご遠慮くださいませ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
ネタバレありですと・・・
とにかく子供のいじめって本当に残酷。
そして、いつも思うのですが、私たち(複数形ですみません)大人になれた人は幸運だっただけ、だと思います。
どんなに収入が高い家に生まれても、どんなに権威のある家に生まれても、関係なく、いじめの対象になってしまえば、皆同様に、ターゲットになるだけで、大人の対応は、恐らく場違い、筋違いなモノになり、そして、エスカレートしていく可能性が高くなり、なんなら陰湿化するでしょうし、非常に恐ろしい。
しかも子供なので、制限が効かない。恐らく結構な進み方をするでしょう。
とは言え大人であっても、やるホモサピエンスはいくらでもいますし、島国根性という言葉の一端を担っていると思います。そして、実は、仲間ではないホモサピエンスを見つけては、それを排除、差別する事で、それ以外の、仲間の結束力が高くなる、という事を無自覚に行っているホモサピエンスがあなたの周囲にも必ずいます、と断言できるくらいうちの国はいっぱいいます。
男女差みたいなモノも結構如実に表現されていて、そこも怖い。
また、結局いくつになっても、排除差別する側のホモサピエンスは、自分がやられる事を想像すらできない、何と言いますか頭が悪い方なので、もう仕方が無いし、離れるしかないと思います。
しかし子供は規則に填められてて、自分の意志が反映されにくいし、躾とかわがままとか言われて結局、ただ単に我慢させられるわけです。
あの監視員の態度は、本当に無いと思うし、監視員の数が足りなさすぎる。
子供っていうだけで大変だし、本当に子育てしようと思える人はエライなぁ。どう考えても私がノラやアベル、なんならいじめっ子側の保護者として、何かが出来る気がしない。その立場を想像するだけで、子供を育てようとすら思わないですね。
是枝監督もうかうかできないのではないか?
2026年2月13日 (金) 12:29
関和亮監督 MGMAmazon Amazonprime
2026年公開映画/2026年に観た映画 目標52/120 4/18
原作を読んでいるので。書籍は本当に素晴らしい書籍ですし、著者かげはら史帆さんが素晴らしい仕事をされているんですけれど、どうやってこれ映画にするのか?が気になったので。
脚本に芸人のバカリズムさんが入っているのですが、この方は脚本書かれる人なんでしょうか?なんでこの人なのか?が不明。
監督も初めての方なのですが、唯一、主演を知っています!鬼邪高校の村山さんじゃないですか!!で、観る事にしました。
忘れ物をした中学生の子が、音楽室に向かうと・・・というのが冒頭です。
この中学生の目線を入れる事を考えた人は、エライ。西洋人を東洋人が演じても大丈夫にさせるアイディアは素晴らしい。
また、こういうアクロバティックな事をしないと、映画にはならなかったでしょうね。
そして全部古田さんが持って行きます。もう役者の格が違う感覚。流石です。
でも俺たちの鬼邪高校村山さんも負けてない。演技としてはアレだし、いろいろ頑張ってる。でも、そういう事じゃなくて鬼邪高校の村山さんだから、それでいいです。出来れば轟にも共演して欲しかったです。
脚本としてもそれなりに面白くなってると思いますし、悪くないけど、凄く嫌な事言うけど、これ書籍で読む方が面白い話しなんです・・・
邦画にアレルギーのある人でも大丈夫ですよ、という意味でオススメします。
2026年2月10日 (火) 09:08
クリスチャン・アルヴァート監督 コンスタンティンフィルム U-NEXT
2026年公開映画/2026年に観た映画 目標52/120 4/17
SF作品が観たくなった時に偶然見つけたので。
が、凄く変なSF映画。パッセンジャーという映画がありましたけれど、似て非なる映画で、しかもSFとあるジャンルを混ぜていて、それは混ぜるな危険!というモノではないのか、と思いました・・・
あまりネタバレなしで言える事が少ないのですが、ノーマン・リーダスが出ています、びっくり。
えっと、宇宙なんで、アレしないとアレじゃない?とか、本当にいろいろあるんだが、タイトルのパンドラムは造語で新しい病気の話しです。
にしても解決しない物事が多すぎやしないか・・・
デス・ストランディングを遊んだ人にオススメします。