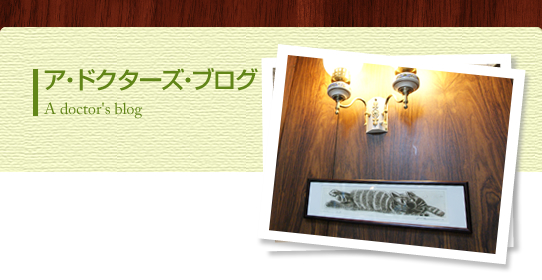ジョージ・ソーンダーズ著 岸本佐知子訳 河出文庫
国民を二分するような大胆な政策、についての説明が無いのに、白紙委任を求めている状況が2026年1月27日なのですが、これから説明されると期待したいんですけれど、しないかも知れません・・・
つまり、本当に白紙委任を求めているわけで、それは過去に同じような事をして、酷い失敗を招いているやり方、人類史上の大失敗を招いたのように感じるのですが、もう正常な判断とか政策とかじゃなく、感情、好き嫌いでしか判断が出来ないこの状況は教育の失敗だと思いますし、ホモサピエンスの限界なのかも。
普通は論理って重要だと思うんですけれど、そういう事よりも感情を優先させるくらい、追い詰められているのかも知れませんし、そもそも食料もエネルギーも何もかも海外への依存度が高いこの国で、難しい事なのかも。
という事を大人の寓話として書かれているこの書籍は2005年に出版されていますけれど、2026年に読むと本当に恐ろしいです。
大人の寓話が読み取れる人にオススメします。
追記
ニュースによると、委員会の委員長が他党にあるそうで・・・ええっと、議会制民主主義を採っているいる以上、制度の問題で、それって制度を変えるしかないのに・・・
結果を正しいもの(もちろん自分にとっての 正義 )にする為には、議会制民主主義を壊したい、という事になるのでは?ルールの中で変える努力をするのではないのでしょうか?議会で協議するために、議員がいるのでは?話し合い、協議する気が無い、という大変に恐ろしい動機を感じました・・・銀河英雄列伝は今こそ読まれるべき書籍なのかも。
本当に恐ろしい。
夕木春央著 講談社文庫
有栖川有栖さんが帯で「この衝撃は一生もの」とまで書かれているので・・・ええ、まぁ誇大広告であろう事は理解しているのですが、何せ初めて読む作家さんだったので。それと、タイトルは素的だな、とも思いましたし。
これ、設定だけ出だしで書きますけれど、まぁ、宣伝でも使われていますからネタバレには当たらないと思いますが、なかなかです。
山深い場所にある捨てられた地下施設、方舟。地下3層構造で、たくさんの部屋があります。しかし地下3層目は水没しつつあり、この地下施設に大学時代の友人7名が泊りに来ると、そこへキノコ狩りで遭難した親子3名が加わり、そしてその夜に巨大地震があり、2つしかない出入り口のひとつが塞がれ、誰かを犠牲にしないと全員が水没する状況になり、そこで殺人事件が起こり、その犯人こそ、その犠牲者になるべき・・・
と、てんこ盛り過ぎるんですね・・・料理なら胸焼けを起こしています・・・
そして、とにかく、登場人物が、凄く、そういうモノだとしても、なんだかなぁと思う行動をとるんですよね・・・
みんなどんでん返しが好き過ぎると思う。
正直、この作品、いわゆるジョン・アーヴィングが言ったとされる、物語はラストシーンから書かねばなるまい、という手法で描かれている気がします・・・そして、どんでん返しの 為の 後付けの理由を作った結果、この作品が生まれたんだと思います。
人物描写もそこまで、ではないし、あくまでミステリなんで、そこに拘泥し過ぎているけれど、だからこそ進化した日本の本格ミステリというジャンルの、進化の袋小路みたいな感覚になりました・・・
いや、逆算とは言え思いつくの凄いけど、まぁ現実にはあり得ないだろ、それは、という大筋なんですよね・・・
地下の施設方舟、同じタイミングで家族と遭遇、巨大地震、浸水があってタイムリミット、殺人・・・どんだけ重ねないとこの状況が生まれないんでしょうか・・・
それと、閉じ込められた後っていわゆる相互監視って起こるモノじゃ・・・安全性への配慮が無さすぎる・・・なんなら少なくとも2名か3名のグループで行動するのが普通!
あと、水位が上がれば同時に浮かんでいけるルートを探すとか、滑車を動かすのに横で動かせる仕組みを作る方が現実的な気がするし、塞がれる仕組みも、そりゃ謎の施設だから、そこまでの設定は要らないかも、ですけれどいくらなんでも、とは思います・・・
とは言え、そういう全てを、日本の、本格ミステリ、という名のジャンル小説として飲み込める人になら、響きそうです。そういう意味ではマッチ棒でお城を作りました、的な凄みはあります。でもどうせ作るならもう少し人が住めたり実用性があった方が、とかいう野暮みたいな話になってしまいます私の感想も。
昔は私も、本格ミステリ好きだったけど、今は遠くに離れてしまったな、という感慨にふける事になりました。
島田荘司、に見いだされた人々のジャンルだった頃は付いて行けたけどね。
この界隈での最も好きな作家で言えば法月綸太郎さんですし、やはり誰にも超えられない島田荘司の「占星術殺人事件」はちょっと頭抜けていますよね。
ミステリが好きな人にオススメします。ただ、味付けがかなりキツいですよ、とは付け加えておきます。
2025年は久しぶりに読書にも少し時間が取れた1年でした。
で、ちょっと自分事ながら驚いたのですが、このブログ、2010年6月からやってて、え?となりました・・・その前にもやっていたのですが、知らないうちにそちらのブログはサイトそのものがなくなっていました・・・gooブログという場所だったのですが・・・その時も1年くらい、やってたと思います。もう思い出せない・・・
その頃、というか若かったころは、多少は趣味が読書、と言えた時期でしたが、ここ10年くらいは全く本が読めない時期でした。
それが久しぶりにそれでも20冊程度で、それは読書とは言わない感覚もあるのですが、全てを相対的に見ると、自分事として、久しぶりに読書に時間を作れた1年間だったと思います。
そのきっかけになったのがアガサ・クリスティーの「春にして君を離れ」でした。本当に素晴らしい本と出合えた事、そして割合すぐにもう1冊、J・B・プリーストリーの「夜の来訪者」を読めた事も僥倖でした。どちらも素晴らしい本で、あまり懐古主義にはなりたくないのですが、そうは言ってもホモサピエンスが生きている意味ってもしかすると、想い出を作る事のような気もしますし、というか他には何もない気もします。今でなければ理解出来ない一期一会の繰り返しですし、そういうモノな気もします。
来年も、というよりは、ここ数年、いやもっと言うと10年くらい前から、もういつ何時亡くなる事になっても、おかしくはない年齢になっていて、その自覚もあり、生きている間に、良い本とめぐり合えれば、と思います。
そしてどんどん、現代の作家の素晴らしい作品と言われる書籍に、距離と感じやすくなった、と言えるでしょう。評価の高い村田沙耶香さんや王谷晶さんの著作の、良いと言われる部分はある程度理解出来ても、そのフレッシュさを感じ取れても、いわゆる古典として評価のある程度定まった書籍と比べて、その興奮なり驚きなりの深度は浅いな、と感じてしまうように、つまり老人になった、という事なんですけれど、なってしまいました。
老人力©赤瀬川源平がついた、という事です。これからも前期改め、中期高齢者として生きて行こうと思います。
身体の老化の進み具合は、人それぞれ。私は比較的身体的老化が早く、精神的には中学生くらいで止まった感覚があり、情けない限りです。
もう数冊読み進めているのがあるので、それを読める幸せを感じています。
筒井康隆著 文春文庫
今年は書籍の整理もしつつ、終活としても整理をし、春にして君を離れを読んだ事で読書熱が久しぶりに高まって、文学部唯野教授をパラパラと読み返しつつ、そう言えば大いなる助走読み返そうかな、という事で、古本屋で新装版を見つけて購入して読みました。
個人的な意見ですけれど、凄く文学部唯野教授と似ている、というかこちらが元祖。
その上で、良く出来てます。
ただ好みとしては、やはり文学部唯野教授が好きですね。
しかし、こういうの本当に上手いなぁ。
そして続編があるらしいので、読んでみようと思います。
それにしても、筒井文学ははっちゃけてて凄い。
これ主人公を誰で読むか?で結構変わってくる話しですし、地方文学同人雑誌って今はネットに移行しているのでしょうか。
ハン・ガン著 きむふな訳 株式会社クオン
初めて読む韓国の作家。もちろんノーベル文学賞をお取りになったから読めるようになったんだと思います。そういう意味でノーベル文学賞はデカいけど、これはどのような賞でも思いますけれど、選考委員の問題を考えてしまいます。が、とにかくうちの国の作品の受け手は『世界の』が付いたり『賞』が付いたりすると観る人が多くなるので、流通するようになるのですが、選考する人の意向が強く反映される場合、歪んだ形になる気がします。
典型的なのが、芥川賞と直木賞ですね。選考委員の、文学ムラへの入村基準だと思ってます。うちのムラに入れて良いかどうか?を決める基準なので、作品の評価では無いと思いますし、アメリカのアカデミー賞はまさに取るべき作品が採らない、もはや何のための賞なのか?関わる人々の関係性の話しに見えます。
それでも、知らない作品、そんな事言ったら、ホモサピエンスの生きていられる時間をいくら使っても、これまでに発表され残ってきた、所謂古典的名作と言われるモノ全てを履修する事はもはや不可能な世界です。出来るだけ吸収したいし味わいたいけれど、ある程度選んでいかないと難しいし、当然受け手にも好みというモノがありますし、この間衝撃を受けたアガサ・クリスティーの「春にして君を離れ」のように人生の経験を積まないと理解出来ない名作もあるわけです。
手に取れる機会を与えてくれた事には感謝しつつ、初めて読む韓国文学でしたが、そういう些末な事よりも、文学作品として、なかなか変わった作品でした。確かに面白い。
連作短編でそれぞれに関わりがあるのですが、恐らく、私が個人的に受け取ったテーマは女性の生き難さ。これに尽きると思いますし、周辺から中心に向けて徐々に語り手が移っていく作品です。
現代の韓国で暮らす会社員の視点から見た妻の変化、それも夢を見た事による変化に戸惑う夫の、一見社会性のある一成人の視点から見た異変なんですけれど、それが如何に一面的であるのか?を考えさせられます。
その後に続く、一般的とは言い難い職種で、しかしだからこそ、かなり踏み込んだ事件が起こるその描写。
最後に明らかになる女性の視点から見た、姉妹から見た場合でも理解不能な中心人物の変化と渇望。
この構成はかなり異質ですし、それなのに気づかされる上手さがあると思います。
文体で言うと、凄く、村上春樹っぽい。言っちゃなんだけど、っぽい。でもそれは翻訳の問題かも知れませんし、もしかするとリーダビリティ高い、という工夫の結果なのかも知れません。
韓国映画は今までにも見てきたけれど文学は初めてだと思いますし、かなりの重さもあり、好みの作家でしたので、もう少し読み込んでみたいです。