プリーストリー著 岩波文庫
とある配信を観ていて、良い文学作品の例のひとつに挙げられていて、しかも全く知らなかったので、手に取りました。そして、読み終わって非常に素晴らしい作品に触れられて感謝しています。1912年の戯曲ですけれど、本当に凄い。やや、やり過ぎに感じるかも知れませんし、今観ると演劇的な予見は出来るかも知れませんが、当時は非常にセンセーショナルに迎えられたと思います。
またこの作者や態度を左翼的という批判はあるだろうと思いますが、何をもって左翼的なのか、かなり微妙に感じましたし、階級社会の中で、しかもイギリスで、紳士的な事を善しとする文化の中で描かれている事を考えると、単に左翼的とは言えないのではないか?と思いました。もっと大きな事について、実際に警部に言わせていますし、そここそがテーマ。と私は感じました。
アーサー・バーリング邸ではその娘シーラと、アーサー・バーリングとは同業者であり同じく工場主で階級社会ではより上のサー・ジョージ・クロフトの息子であるジェラルドの婚約の宴が、父バーリング、妻シビル、娘シーラ、息子エリック、そしてジェラルドの5人参加して開かれています。食事も終わり給仕であるエドナが食器を片付けている所に・・・というのが冒頭なんですが、非常に演劇的で上手いです。
私はどんでん返しが強すぎると、どんでん返しという刺激に麻痺してしまい、もっと強いモノを!という傾向に強い危機感を感じます。何故なら、どんでん返しの為の、どんでん返しが多すぎるようになってきていると感じるからです。あくまで、どんでん返しは結果であって、作為的に作られると、それは作者の都合で組み込まれているだけじゃないか、と感じてしまいやすいと思うからです。
どんでん返しの、為の作品は、志が低い、という事です。もっとテーマやキャラクターが生きて、その上そのテーマやキャラクターに関連がある出来事や事柄が、ひいてはどんでん返しに見える、というモノが望ましいのではないか?と思うのです。
この1921年の作品はそういう作為を、感じにくいです。もちろんテーマに沿って展開していますし、驚きがありますけれど、おそらくそれよりも、警部の退場の際の言葉を言いたいが為に作られた作品。
これ、現代に設定変えられないですかね。凄く面白そう。で、多分家族の話しにするのは難しいし、SNSも絡めたいです。
何となく、学会、それも社会科学的な学会で集まった世界各国の代表的な5名に対して、とすると面白そうなんだけど、捜査権的な存在が難しい。
結局国家を超える統治権力は存在しないが、その国家の統治の限界は露呈していて、企業資本は恐らく国家よりも強く、国家を超えて資本を移動できる。その事だけでもどうにもならないのに、国際的な枠組み、に拒否権がある状態で、そもそも常任理事国の権利が強すぎる問題も解決できてないので難しいですかね。
それにしても見事な脚本でした。
善性について考えてみたい方にオススメします。
それと、この来訪者って言葉、私がタイトルに出てくる作品で知ってるのってもう1つしか無くて。という事は当然、この作品のタイトルから取られているんでしょうね。
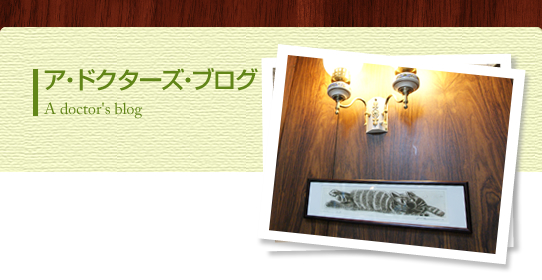






コメントを残す