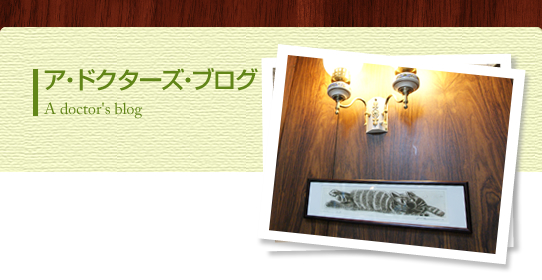エミリ・ブロンテ著 小野寺健訳 講談社古典新訳文庫
まず、古典作品にもう少し触れても良いのでは?という気持ちが常にあります。趣味は読書、と言えた時代もありましたが、老年になってもう少し触れておけば良かった、と後悔しています。なので、何処から手を出すかなんですが、エメラルド・フェネル監督が来年マーゴット・ロビー主演で映画化されると聞いて、興味を持ちました。
あと、古典の中でも比較的名前が有名。嵐が丘、名前が強いです。そして、何の予備知識も無いです。何の話なのかも知らなかったです。私が読んだ事がある古典作品って、レ・ミゼラブル、カラマーゾフの兄弟、アンナ・カレーニナ、ボヴァリー夫人、カフカは城とか審判とかいろいろ読んでますけど、スタンダールもトーマス・マンも読んでない、文学弱者です。
でも考えてみると、何が古典なのか?結構複雑。オイディプスとか三国志は古典で間違いないでしょうけれど、シェイクスピア作品って1600年辺りだったような・・・それだとしてもたかだか400年前で、これを古典と呼んでよいのか?微妙。で、wikiで調べても、確実に、こう、と定義付けられていません、おそらく、文学的評価の定まった作品を、古典文学と呼んでいるのだと推察されます。
だとすると、名前が有名な「嵐が丘」も当然古典文学に入るでしょう。それにイギリスの文学は、それこそ「高慢と偏見」で有名なジェーン・オースティンもいますし、最近読んだアガサ・クリスティーの「春にして君を離れ」は最高の文学作品だと思いましたし、ウィリアム・ゴールドウィンの「蠅の王」だって素晴らしかったし、面白いに違いないし、知らなかった何かを知る楽しみがあるはず!
という期待値が高すぎたのかも知れません。
あらすじの紹介は他で見て貰うとして、いろいろ気になり過ぎる事が、たくさんあります。しかしどれもネタバレを踏んでしまう可能性が高いです。
アテンション・プリーズ!
ここからは、ネタバレありの感想です。未読の方はご注意下さいませ。
ので、ココからは「嵐が丘」という文学作品のネタバレと、あくまで文学弱者の私個人の感想が綴られますが、あくまで個人の感想です、作品を穢すつもりはありませんが、何で?どうして??があまりに多すぎました・・・そして非常に批判的な感想ですので、そういう駄文は読みたくない方はスルーしてください。感性の死んだ高齢者の文学弱者が戯言を述べているだけです。
文学作品の進歩の証、つまりまだ文学的な創意工夫が未熟だった頃のテクストとしての存在、とも言えると思いました・・・
まず、チョイスしたのが講談社古典新訳文庫で、これは読みやすかったから、です。冒頭をいろいろ岩波や新潮他数社比べて決めましたけれど、主な人物関係図、が最初に載ってて、しかも栞にまで、登場人物の名前と説明があって、イイ!これ!と思いましたが、作中の誰が、誰と結婚して子供が生まれるんだ、を知って読んでいると、全然楽しくないです、結果を知ってるのだから・・・
なんでこんな作品が現代にまで残っているのでしょうか?
そして、登場人物の全員が、頭が悪い、獣のような、その場の雰囲気と感情で行動を起こし、且つ、即直後に後悔する、みたいなのが多すぎる!!まるでおかしな行動を全員が取るために、凄く頭が悪い人、ばかりに見えるんです・・・
感情の波の高低差が激しく、毎秒毎に感情がかき乱され、精神的に安定している人が、ほぼいないんです・・・あ、何度も言いますが、私個人の感想です、この文学作品の評価を貶めるモノではありません。ありませんが、この作品の、何を、評価しているんでしょうか????
みんな都合良く、退場していきますし、都合良く誕生してきます。そして復讐譚とか悲劇とか言われていますけれど、どこに悲劇性があるのか?全然分からないです、私には。
恋愛の話し、確かにある種の恋愛の話しではあると思いますけれど、細部、何故恋に落ちたのか?何故その人を好きになったのか?の細部が全く書けていないと思うのです。もう全員が当然のごとく一目惚れ一択。潔ささえ感じます。で、それが作者の物語にツイストをかける為、にしか見えないので、稚拙(と古典作品に思う私のなんと思い上がった感想!でも思っちゃったんだから、そうとしか感じられないんだから仕方ない・・・)とさえ感じました。
唯一、執着の話し、というのであれば、納得します。でも、何故ここまでの執着なのか?と問われたら、説得力があるのは、
①ヒースクリフの育ち(孤児からの、実子よりも優遇された過程、その後のネグレクト せめて、何故実子よりも優遇されたのか?の理由くらいは明示して欲しい)
と
②キャサリンがエドガー・リントンと結婚を決めた事をネリーに語った部分をたまたま聞いてしまった
とこの2点だけ、ここだけは納得出来ますが、それも発端に過ぎず、そこから何がどう発展した、とは言えないと思います。その時の感情だけで、ここまで執着しますでしょうか?
なんというか、また世界の半分以上を敵に回すんですけれど、素直に感情を委ね、登場人物たちに感情移入しているのであれば、感情をグリップさせられて、身を委ね、感情をグリグリとコントロールされる心地よさ、あるかも知れません。が、あまりそのコントロールも上手くは無いと感じました。薄っぺらな表現で申し訳ないけれど、幼少期のホモサピエンスで書籍や文章を読み慣れない人なら、感動するかも。
娯楽の無い世界で、恋愛や人生を語れる時代の話しであれば、キリスト教がその世界の隅々までいきわたり全員がある一定水準以上信仰している世界であれば、話題になるかも知れませんが、恐ろしい事に、発表当時は全然売れても話題にもならなかったようで(wiki調べ)本当に、何故この小説が悲劇的で古典として生き残っているのか不思議。
レ・ミゼラブルのような世界観と広がりがあるのであれば、ホモサピエンスの普遍性みたいなモノも含まれますし、当然恋愛だの結婚だの生活の話しもあれば、政治や活動、信念、信仰の話しもあり理解出来るのですが、この小説はちょっと勢いに任せて書かれた、推敲が足りない印象を受けるのです。
物語で言うツイスト、予定調和を崩す、どんでん返しみたいな事も、伏線からの、というわけでは無くて、とにかくどんどん数で勝負みたいな感覚があり、整合性とか、あまり感じられません。そもそも婚姻関係とか法律関係、医療関係についてもあまり詳しくは無い印象なのに、結構重要なポイントで、さらり、とそうなった、となるのが続くと、どうしても続きが気になるというよりも、そうですか、となってしまいます。
がそれもこれも、本当に戯言であって、時代も違うし、読んでいる書籍も違うし文化も違う世界の話しを一方的に現代的視点から批判するのも筋違いでしょう。
入れ子構造で、語り手が出てくるまでの感覚と、いわゆる信用ならざる語り手、当時として新しかったと思いますし、斬新。
ヒースクリフという、白人社会に現れた、白人上流階層の教養を得る機会を得た、非白人というのも新しいかも知れませんし、粗野、野生の魅力をいうのも珍しいのかも。
また、悪魔とかサタンと言われるセリフが多いヒースクリフの、悪魔というダークな魅力、あるのかも。
と良い所を挙げたいのだけれど、全然出てこない・・・そもそもなんでヒースクリフをミスター・リントンが拾ってきて育てようと思ったのか?も不明だし、3年ほど消えてた間の詳細どころか雰囲気も分からない、この頃の階層を超えるのは、よほどの事だと思いますけれど、3年じゃ難しいと思うのですが、というか、この3年こそ、書かれるべきビルドゥングスロマンになりそうなのに、不明です。出自も不明なまま・・・
一緒に育てられた幼馴染で兄弟だけど血が繋がらない魂の連帯者、という妄想ももしかしたら新しかったのかも知れませんね。一緒に育ったのなら、もう少し兄ヒンドリーにも愛まで行かずとも、もう少し好意的な進言とか関りを持ってあげればよかったのにね。
でも、幼馴染で兄弟で血が繋がらない、幻想というと、まぁそんな事は関係ない、と言われるでしょうね。つまり感情、この作品が好きな人に何を言っても伝わらない気がします、議論にならない。
野生児の魅力とかもダメなんでしょうね。ヒースクリフの魅力はそんな低俗じゃない、と怒られそうです。幼馴染の血の繋がらない異性幻想も、きっと怒られるな。
ヒースクリフは、本当に、ヒンドリーに復讐出来たのでしょうか?だらだらと生き永らえた、とも取れるし、別にすべてを暴力で解決とは思わないけれど、野蛮な人で悪魔なんだけど、結構ヒンドリーに対して優しい、とも取れる。全然復讐な気がしないし、この登場人物たちは、かなり気が短く、思考よりも行動を優先するのに、殺す、とか痛めつける、とかの描写はほとんどない。血が流れる事も稀。ギャンブルを楽しんで野垂れ死に、みたいに見えるけど、どうなんだろう。
もしかすると、これがイギリスの、英国の田舎の閉鎖的な、因習的な感覚なのかも知れませんね。そういう意味での田舎の怖さはちょっとある気がします。
あと、神がいるから悪魔が対立構造として必要なだけで、ヒースクリフの執着が、悪に、なんなら愛に見えてる人、いるんでしょうね。私はただの執着だと思うし、みんな都合良く死んで退場するの、ご都合主義的に見えるけれど・・・
あと、貴族というか上流階級だからこそ、の自分はこうなんだから、こうしてくれて当たり前、感覚はかなり触りますね、紳士と淑女の国も、田舎はこんな感じだったのでしょうか?でも同時代の「高慢と偏見」のベネット氏は全然違ったような・・・
それと妊娠問題も、強い違和感。
妊娠に至る部分は、まぁいいでしょう。けれど、妊婦であるという情報がほぼでないで、ヒースクリフとキャサリンが最後に抱擁するシーンを頭に想像していたのに、急にキャサリンが亡くなり、同時にキャシー誕生、え、だとすると、さっきの抱擁シーンは妊婦って事??となり、本当に、萎えます。妊婦だから萎えるとかじゃなく、時系列的にも、作者のご都合主義に、萎えるんです。もっと上手く書いてくれよ・・・推敲が足りてないんじゃ、と邪推したくなります。
ヒースクリフのラストも、それと、キャシーとヘアトンの結末も・・・なんか内輪の話しばかりで、死ぬために登場させられてる感すらあるリントン・ヒースクリフの哀しみがより際立って感じますね・・・急にねじの回転みたいになるし。
この講談社古典新訳文庫の訳者小野寺健さんの解説でも、凄く嫌な表現を使うので引用しちゃいますけど
下巻 解説 416P
しかし、一度読んだだけでそこまでの理解に到達するのは難しい。魂の底の底を探って、えぐり出す精神の強さ鋭さは、著者が命がけで表現した質のものだ。
うん、魂については本当に何も言えません、私の魂があったとして、確実に低俗だもの。その魂を感じろ、Don’t Think Feelという事であれば感受性の無い私は多分無理で、だからわかんないんだと思います。Don’t Think Feelの考え方も諸説あるんですけれど、この場合は普通に、考えるな感じろ、です。
分からない私が悪い。
が、小説というジャンルの進化を感じる、古典としての何かを、感じました。まぁ同時代と言っても良い、ジェーン・オースティンには書けてるから、ちょっと違う気もするけれど。