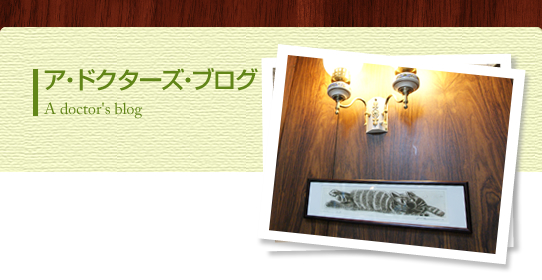辻田真佐憲著 講談社現代新書
今年も敗戦の日ですね。なんで終戦という言葉を使うのか?理解が出来ません。多分、占領軍でなくて進駐軍という言葉を使うのと同じように、現実に目を向けられない精神的弱さなのではないか?と個人的には思います。
今作も非常に感銘受けました。元々、辻田さんの書籍をこれまでも読んでいて好みの傾向ではあるものの、それなりに、多少は先の戦争関連の書籍を、少ないながらも読んできましたが、腑に落ちる読書体験でした。
ある種の分断が既に生まれて久しいですし、基本的には、もう少し話し合うとか合意を目指す、という事が図れたらいいのに、と思いつつ、面子が大切だったり、内向きの、支持者からどう見えるか?を優先してきた結果なんだろうな、とは思いますが、残念ながら、保守と革新的、左右の分断は埋まらないんだろうな、とは思います。埋まらなくて当然なんですけれど、もう少し極端にならない、より中間的な立場がなさ過ぎる、とは思います。明治や昭和初期の頃なら、右派左派の垣根を超えての話し合いが持たれていた感覚があるのですが・・・より先鋭化し、SNSとかで多数の人間に見られる状況になり、ネット空間に法治が及んでいない、無法地帯だからだと思いますけど。
ある事象に対して、その解釈はいくらでも成り立ちますし、その意図は、その事象を起こした人の日記(今ならSNS、動画配信)でさえ、信頼おけるか微妙だと思います、嘘を書くことだって十分にありうる。永井荷風の断腸亭日乗でさえ、検閲を恐れて、黒塗りしたりしていた部分があり、その事を自身で恥じてから、切実な思いを綴った、と言われているけれど、嘘が混じっていない、と断言は出来ません。
それでも、大筋で認められる、現在の資料の所、と言う中腰力、判断保留の態度が求められるし、大人な対応で教養というものだと思うのですが、未定を許さないというか、白黒はっきりさせろ、という圧力が強く、我慢できなくなって来ているんでしょうね・・・
本書では、何が戦争の発端は何となっているのか?またはどうしたら止められたのか?さらに日本に正義は無かったのか?という非常に気になる部分を紐解いていきます。
どの部分も刺激的ですし、知らなかった事を知る楽しみに満ちています。歴史にIFは無くとも、この立場で何か他の選択肢はあったのか?と考えるのはなかなか面白味があり、個人に体験を引き寄せる我が事に出来る作業だと思います。
私が最初に先の大戦について気になっていたのは、何故こんな負け方なのか?という事だったのですが、いわゆる総力戦研究所の結果を、4倍程度なら精神力で成せる、といった発言に疑問を感じたからです。ですが、本書を読むと、なかなかに東條英機の置かれた状況も、そう言わなければならない苦しさを理解できました。
このように、歴史に対して、あくまで現在の感覚での解釈に他ならない、と著者が言うように、PTSDの概念がない世界であれば、ある種の現象を精神疾患とは捉えずに、根性論で解決したでしょう。それを無意識になってしまうのを、理解しましょう、という事なのだと思います。
歴史とは、連綿と続く継続、そしてリアルな選択の結果であり、過去を変えることはできず、その解釈、失敗を認めて、だからこそ改善を求めていく他ないのではないか?と感じました。
ただ、認めるのが、出来ないんですよね・・・私もホモサピエンスですし、認められない出来事たくさんあります。個人主義だからなのかも。漱石の言う感覚ですね。
最終的には、国民的な物語の必要性を説いています。最初、非常に疑わしく、ちょっと辻田さん、と思ったのですが、ナラティブ、確かに忙しく、仕事、子育てなどの生産的活動をしている人々のことを考えたり、有権者の5割近い人が無党派層な国家ってかなり少数派だと思われます。「大衆の反逆」のオルテガの言う大衆がいる事、そう考えると、必要なのかも。みんなが読書出来たり、関心を持ち続けることは難しいですし、結局の所、先の戦争の体験者は少なくなり、必ずいなくなるわけで、しかもその間、それなりに平和が続いている。それこそ「不正義の平和と正義の戦争」の話だとしても。戦線の後方だとしても。それを享受しているわけですし。
などといろいろな事を考えさせられる読書体験でした。
新書ですしあっという間に読めます。
同時に、ドナルド・キーン著「作家の日記を読む 日本人の戦争」の事も思い出しました。
先の戦争が気になる方に、歴史が気になる方に、オススメします。